
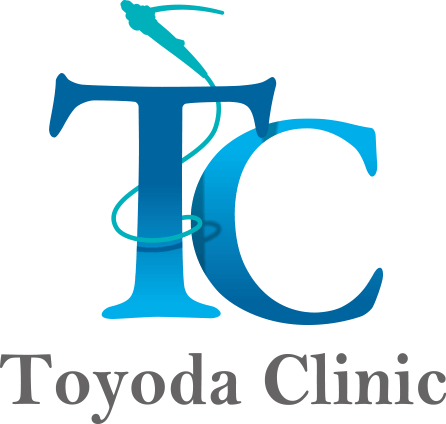
大腸肛門病学会認定施設
直腸脱
〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3丁目2−3 ヴエルビュ溝の口1F Access
お問い合わせはこちら
044-850-3334

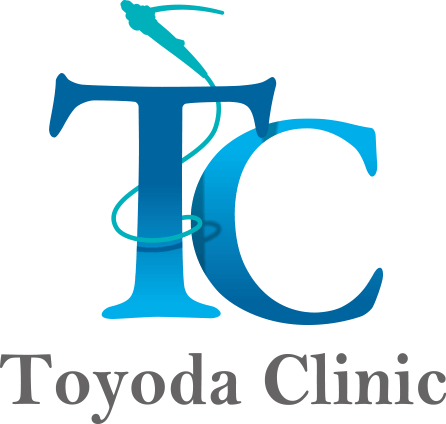
大腸肛門病学会認定施設
直腸脱
川崎市溝の口の豊田クリニックでは、直腸脱 の診療に対応しています。直腸脱は直腸の一部または全体が肛門から突出する疾患で、排便時の違和感・痛み・出血・便通異常を伴うことがあります。原因は骨盤底筋の弱化や慢性的な便秘・下痢などで、高齢者や出産経験のある女性に多く見られます。治療は生活習慣改善や骨盤底筋運動などの保存療法から、必要に応じて腹腔鏡手術や直腸固定術などの外科治療まで、症状に合わせて行います。
直腸脱は、直腸の一部または全体が肛門から外に突出する状態であり、生活の質に大きな影響を与えることがあります。本ページでは、直腸脱の詳細な説明、原因、症状、治療方法、予防策について詳しく解説します。また、よくある質問にも回答し、患者様が安心して治療に臨めるようサポートいたします。
直腸脱は、直腸の一部または全体が肛門から外に突出する疾患を指します。この状態は、直腸を支える骨盤底筋や靭帯の弱化により発生します。直腸脱には外脱(外部に直腸が突出する)と内脱(直腸が一時的に突出する)があります。外脱の場合、直腸が肛門から完全に外に出てしまい、自己戻しが困難になることが多いため、早期の治療が必要です。直腸脱は主に高齢者に多く見られますが、若年層でも慢性的な便秘や下痢、骨盤底筋の弱化などが原因で発症することがあります。直腸脱が進行すると、排便時の痛みや違和感、出血などの症状が現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。
直腸脱の主な原因は、直腸を支える骨盤底筋や靭帯の弱化です。以下に具体的な原因を挙げます。
これらの要因が複合的に作用することで、直腸脱が発症しやすくなります。
直腸脱の症状は、脱出の程度や進行状況によって異なります。主な症状は以下の通りです。
直腸の一部または全体が肛門から外に出ている感覚を感じます。外脱の場合は、実際に直腸が肛門から出ている状態が確認できます。
排便時に痛みや不快感を感じることが多く、特に重度の直腸脱では激しい痛みを伴うことがあります。
脱出した直腸が擦れたり、刺激されたりすることで出血が生じることがあります。
直腸脱が進行すると、便秘や下痢の症状が悪化しやすくなります。
脱出した直腸が神経を圧迫することで、肛門周囲にしびれや感覚異常を感じることがあります。
骨盤底筋の弱化により、尿失禁が発生することがあります。
重度の直腸脱では、貧血や体重減少などの全身症状が現れることもあります。
軽度の直腸脱や初期段階では、保存療法が選択されることがあります。
骨盤底筋の緊張を高める薬剤や便秘を改善する薬剤を使用することで、直腸脱の進行を防ぎます。ただし、薬物療法はあくまで補助的な治療として用いられます。
重度の直腸脱や保存療法で効果が見られない場合、手術療法が必要となります。主な手術方法は以下の通りです。
直腸脱は、直腸が肛門から外に突出する状態であり、早期の診断と適切な治療が求められます。治療法は症状の重さや脱出の程度に応じて選択され、保存療法から手術療法まで多岐にわたります。再発を防ぐためには、生活習慣の改善や骨盤底筋の強化が重要です。症状が疑われる場合は、速やかに専門医に相談し、適切な診断と治療を受けることをお勧めします。直腸脱は適切に管理することで、生活の質を維持し、再発リスクを低減させることが可能です。